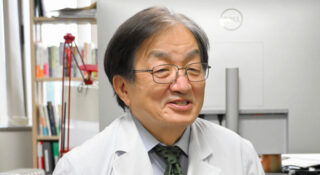どうほく談話室
富良野協会病院長 古川博之さん(71)
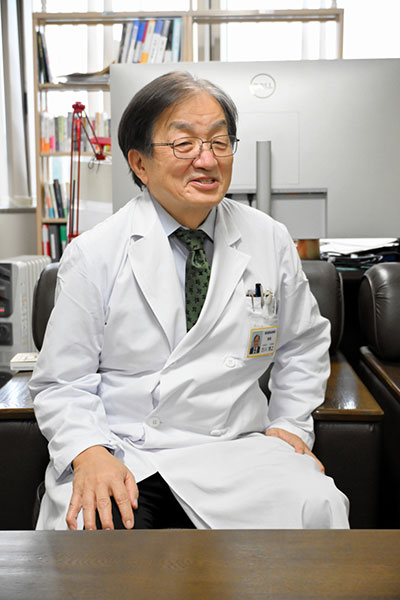
旭医大での経験 新天地で生かす*医療機関 切れ目ない連携を
【富良野】富良野地方の基幹病院である富良野協会病院の院長古川博之さん(71)は、旭川医大病院長を務めた移植医療のエキスパートだ。北海道を代表する観光地を抱え、外国人患者も急増する変化の中で、今夏から院長を担い、地域の医療を地道に支え続けている。取り組む課題や目指す方向性を聞いた。
―7月の院長就任から見えてきた課題は何でしょうか。
「着任してまず感じたのは、地域の病院ごとの役割を改めて確認し、顔の見える関係をつくる必要があるということです。富良野圏は急性期から在宅・介護までの医療資源が限られ、連携強化が不可欠です。急性期は当院で受け入れ、慢性期は他院で診てもらえるように、患者をシームレスに(切れ目なく)つなげられる体制づくりを進めています」
―どんな連携を考えていますか。
「一例として、嚥下(えんげ)機能の検査を必要とする患者を周辺の医療機関から短期入院で受け入れる仕組みを検討しています。当院には嚥下造影検査ができる設備と人員があるため、撮影と評価を行い、結果を持って元の病院に戻っていただく形です」
―スノーリゾートを抱え、上川管内でも外国人患者の受け入れが特に多い病院です。
「言葉の壁や事務手続きの複雑さなどが現場の負担となっています。ニセコ地区(後志管内)の病院を参考に、当院でも通訳の準備や、受診や会計の手続きを説明する文書制作に取り組みます」
―赤字経営が続いています。
「赤字の背景には、地域医療を支えるために十分な診療報酬が支給されていないという制度的課題があります。また、人材不足が深刻化しており医師、看護師をはじめとする医療職の確保も地域の大きな課題です。そのため、離職率を下げて経営改善につなげることを目的として、コーチングを導入しました」
―コーチングとは。
「スタッフが自分の役割や価値を共有し、互いに意見を出し合いながら主体的に動くチームをつくるための関わり方の指導です。旭川医大病院長時代に病院で導入した際には、閉塞(へいそく)感のあった職場環境が改善し『雰囲気が良い』と、見学に来た学生の新規採用につながりました。当院でも看護師不足から一部病棟の休止が続いており、人材が定着する環境を整えることは確かな経営改善につながると考えています」(聞き手・川上舞)
*取材後記
「この地域で暮らす人に、できる限り『富良野で完結できる医療』を届けたい」と語る古川院長。医療資源が限られる地域の中で、近隣の医療機関と手を取り合い、地域全体で地域医療を支える形を探ろうとする姿勢が印象的だった。
ふるかわ・ひろゆき 1954年福岡県田川市生まれ。80年神戸大医学部卒。2010年に旭川医大教授、18年に同大病院長に就任した。22年からは同大理事・副学長を務めた。肝臓外科が専門で、肝臓移植を手がけてきた。
※掲載情報は、取材当時のものです。閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、予めご了承ください。