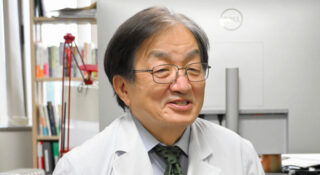どうほく談話室
士別・イナゾーファーム社長 谷寿彰さん(42)

地域課題解決に「耕すラボ」設立*地場産品 価値高め次世代へ
【士別】士別市多寄町でカボチャやトマトなどを栽培するイナゾーファーム社長、谷寿彰さん(42)は、今春、研究開発部門「耕すラボ」を立ち上げた。専属スタッフを新たに採用、栽培過程のトマトの副産物を利用した新商品開発などに取り組む。6次産業化の一歩先を行く「次世代農業経営」への挑戦について聞いた。
―どのような研究に取り組むのですか。
「主な研究対象はトマトです。トマトの栽培時に除去する脇芽は新鮮で病気もなく、有機栽培のため農薬リスクもありません。これを新たな用途で商品化できないかと検討しています。生ごみの活用など、地域の課題を拾い上げ、解決することで、社会で使える資源に変えていく発想で研究を進めています」
―環境負荷の軽減を重視していますね。
「燃料と化学肥料を減らすことが環境対策のポイントです。この地域は美深粘土層で土質が重く、作物を良く育てるには土を砕く必要があり、燃料消費が多くなりがち。土質に合う機械を導入しています。ここで解決できたら多分どこでもできるんですよ。生ごみ肥料の活用による化学肥料の削減も研究テーマです」
―有機農業に力を入れていくのでしょうか。
「有機だから良い、農薬を使う慣行農業だから悪いという固定観念にとらわれず、フラットに考えています。大豆では、有機と慣行で収量を比較したところ、大きな差はありませんでした。有機で実践した栽培法は除草効果が高く、慣行でも応用できます。農薬も原理を理解して使わないと効きません。どちらの農法からも学べることがたくさんあります」
―地域課題を資源に変える考え方の背景は。
「山形の実業家、山中大介さんから『地方の課題はすべて資源に変わる』という考え方を教わりました。地方の課題は、何かを作り出す過程の中にあり、これを解決すると、ソリューションとして社会で使える資源になります。私自身、以前は『地方は終わり』と思っていましたが、今は違います。地球温暖化で本州での生活が困難になる中、北海道は50年、100年のスパンで見れば、むしろ人が増えると本気で思っています。この地域が好きだからこそ、可能性を信じたいんです」
―「次世代農業経営」で何を目指しますか。
「農業を中心に、関連事業を連携させる経営です。例えば、地元食材を活用した飲食業の計画があれば、不動産取得から運営サポートまで一体的に手がける。農業と周辺事業を組み合わせ、地元産品や地域の価値を高めたい。農業はいろいろなことが試せるワクワクするビジネス。この遊び場を次世代に引き継ぐのが使命だと思っています」(聞き手・矢崎弘之)
*取材後記
取材の終わりに、谷さんは、商談や営業を一手に担う妻への感謝を語った。「東京出身の妻の言うことは農村の常識とは異なるが、社会常識に一番近い」と経営上の判断を尊重し、「妻が働いた方が売り上げが増える」と家事を積極的に担っているという。伝統芸能、日向神代神楽の伝承活動などでも活躍。話の節々に、農業を軸に地域を盛り上げようという思いがあふれていた。
たに・としあき 1982年、士別市生まれ。北大大学院農学研究院修了。農家の3代目として2007年に就農。その後、北大(旧札幌農学校)の大先輩新渡戸稲造にあやかり「イナゾーファーム」と命名、19年に法人化し、社長に就任した。妻、江美さん(39)と1男3女を育てる。
(2025年05月19日掲載)
※掲載情報は、取材当時のものです。閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、予めご了承ください。