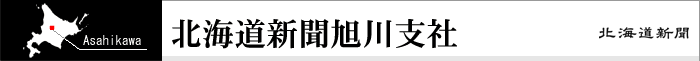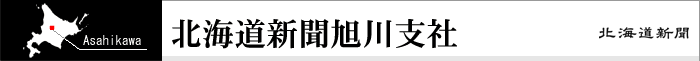|
つるが・みきお
1945年、函館市生まれ。ヤマハミュージック北海道で旭川支社長、常務などを歴任後、退職。オーナーが高齢となった旭川の街頭放送を引き継ぐため、2005年に「アイケム」を設立した。旭川音楽振興会会長、北海道音楽大行進実行委員長などを務める。 |
中心街を歩くと聞こえるあの音。商店のPRや行政情報などが音楽に乗って流れる旭川の街頭放送は60年を越す歴史がある。電柱に取り付けられたスピーカーの数は1000を超え、道内最大規模。発信している企画会社「アイケム」の敦賀幹夫社長に、街頭放送がまちづくりに果たす役割について聞いた。(聞き手・旭川報道部 西村卓也、写真・打田達也) ――いろんな放送を耳にしますが、全部で何種類あるのですか。 「だいたい100種類ぐらいあります。同じものを繰り返すのですが、1時間で約70件、朝8時から夜7時半まで流しています」 ――放送する、しないの基準はあるのですか。 「聞いて不快に思うようなものや、ギャンブル的なものは避けるようにしています。まちへの影響を考えて依頼を断ることもありますよ」 ――放送について市民からの反響はありますか。 「耳になじんだ放送については、やめないでほしいという声が寄せられます。依頼主の企業の中には、顧客が継続を求めるので、他の広告を削っても街頭放送はやめられないという話を聞きます」 ――私は「あー、ワヤだわー、買物公園でジデンシャ乗ってー」と、女性が北海道弁で通行マナーを促す広報が印象的でした。 「あの放送は今年始めたものですが、自転車に乗って買物公園を通る人が減ったと聞きます」 ――内容について社長のこだわりはありますか。 「私は長年音楽に携わってきたので、音楽文化の発信に努めています。広告とは別にいろいろな音楽を季節に合わせて流します。1月は毎年、旭川のイメージにぴったりの『雪の降るまちを』。外国からの観光客向けに英語、中国語、韓国語の放送もあります」 ――歴史ある街頭放送ですが、近年の特徴は。 「機材がオープンリールデッキからデジタルに代わり、放送の幅が広がりました。急なニュースを流すときは録音をしてテープを切り替える必要がなくなり、すぐに対応できます」 ――まちにとって街頭放送の役割は何ですか。 「まちを歩く人に情報を直接、繰り返し伝えるのが特徴です。災害時には街頭放送を通して市民に注意を促せるよう、市役所と協定を結んでいます。古いイメージがありますが、東京などでも効果が見直されているといいます」 ――帰省した人は懐かしさを感じるでしょうね。 「旭川はほかのまちに比べて中心部の騒音が少ないため、街頭放送の存在感が大きいのです。なくなれば寂しくなるのでは。活気あるまちづくりに一役買いたいと思っています」
|